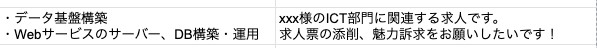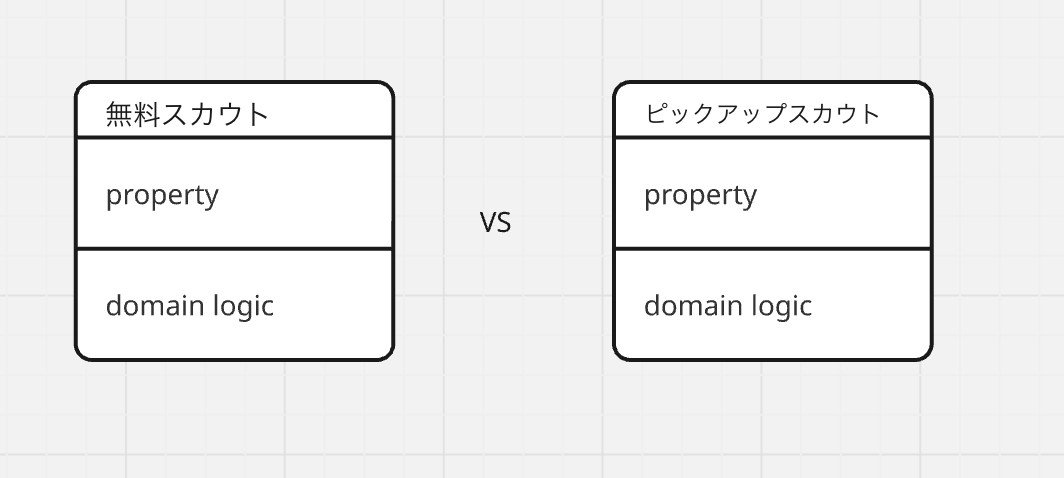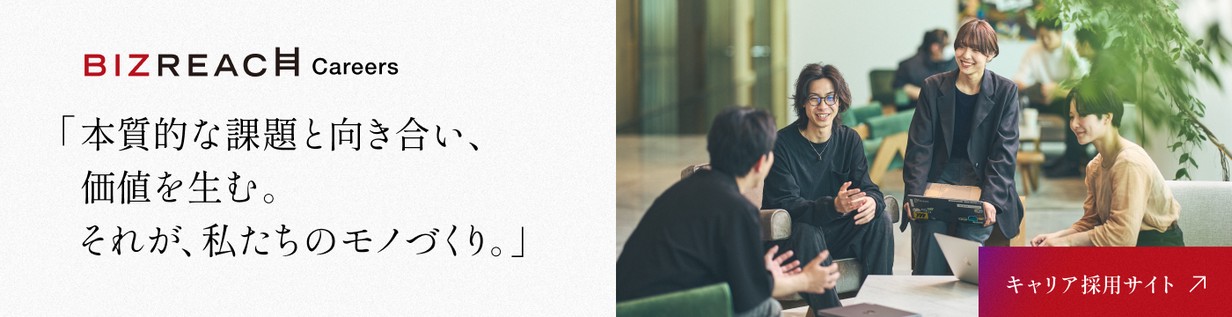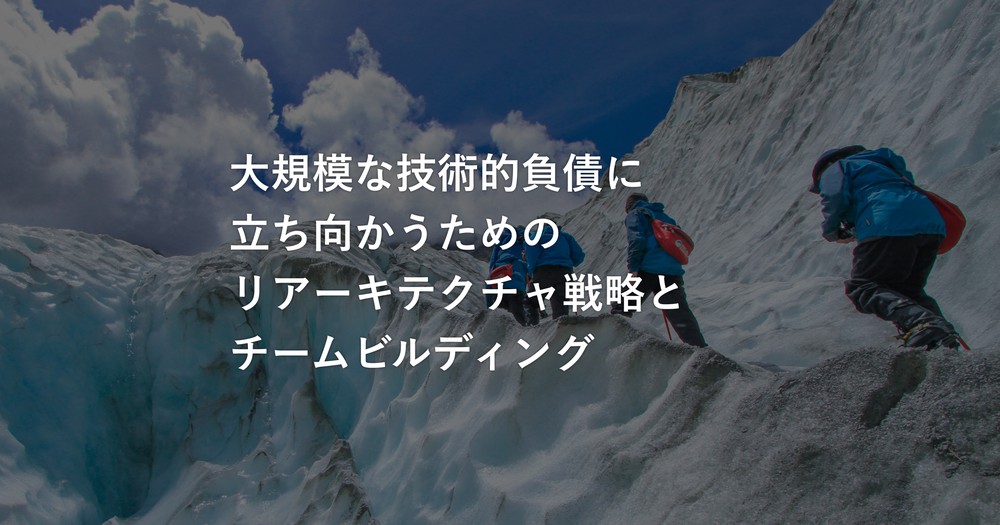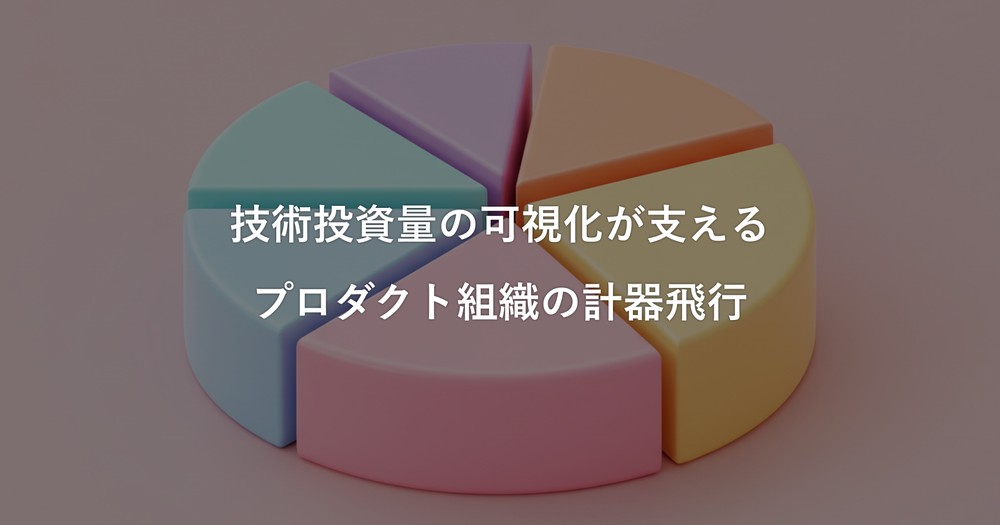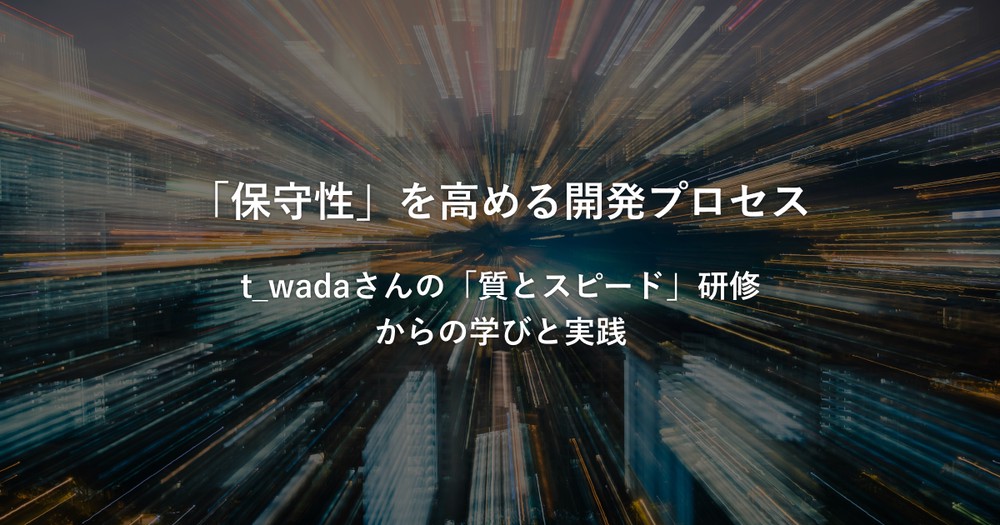はじめに
この記事では、「ビズリーチ」の採用企業様向けプロダクトを担当する開発チームが、2024年末にビジネス組織の地方拠点へ出張した際の様子をご紹介します。出張した目的や現地での取り組み、そして出張前後での私たちの変化についてお伝えします。
「もっとお客様の生の声を聞いて開発したい」「ビジネスの現場で何が起こっているのか肌で感じたい」といったことを、プロダクト職なら一度は感じるのではないでしょうか。 この記事が、組織の壁を越えて連携し、より良いプロダクト開発を通じてユーザーに価値を届けるための一助となれば幸いです。 今回、各拠点へ出張したプロダクト職を代表し、3名の執筆メンバーがそれぞれの体験を振り返りました。
プロフィール
永德 泰明
新卒8年目エンジニア
「ビズリーチ」の採用企業様向けプロダクトのグロース開発を担当
趣味:登山、料理
岡﨑 拓哉
中途入社3年目エンジニア
「ビズリーチ」の採用企業様向けプロダクトのリアーキテクチャ開発を担当
趣味:読書、娘と戯れる
野間 優人
中途入社4年目エンジニア
「ビズリーチ」の採用企業様向けプロダクトのグロース開発のQAを担当
趣味:ゲーム、推し活、フットサル、サッカー観戦
エンジニアが地方拠点へ出張する背景
Visionalグループの従業員数は2024年7月時点で約2,000名規模です。採用支援を担うビジネス組織は、現在は全国6拠点(首都圏・関西・名古屋・福岡・静岡・中四国)に拡大しています。拠点が増え組織が大きくなるにつれ、開発チームは現場での利用シーンやお客様の生の声に直接触れる機会が減りつつありました。 特に地方拠点では、お客様の属性(業種・企業規模)や採用プロセスが首都圏と大きく異なります。そのため、数値上の利用率は把握できても現場のリアルなニーズや利用実態といった定性的な情報を掴みづらいという課題がありました。結果としてお客様へ新機能の価値の共有が遅れてしまうという課題が生じていました。
この課題に対し、まずプロダクトマネージャー(以下、PdM)が先行して地方拠点を訪問し、情報共有やヒアリングを通じて先程の状況の改善を図っていました。その上で、プロダクト開発に関わるエンジニアやデザイナーが直接現場に足を運び会話する重要性を感じ、PdMから「開発メンバーも現場を見に来ませんか?」という提案があり、これをきっかけにエンジニアの地方拠点出張が実現しました。
目的は、エンジニア自身が一次情報に触れながら、プロダクトをよりお客様に活用してもらうため、ビジネス組織との双方向の関係性を構築することです。
出張での具体的な取り組み
ここからは、各拠点の出張中にプロダクト職が現場で実施した具体的な施策を紹介します。
お客様の課題ヒアリングと機能活用提案
お客様の人材採用やその支援に関する課題について、ビジネス職社員へヒアリングを実施しました。 ヒアリングは、PdMがファシリテートし、エンジニア・デザイナーが補足として質問を行う形式で進めました。 エンジニアの視点からは、お客様が抱えている課題に対し開発した機能がどの程度解消に寄与しているのか、 また不満を感じられているポイントは何かを把握でき、プロダクトや機能の価値を多角的に捉え直す機会を得ました。 ビジネス職社員からは、ヒアリングの過程でプロダクト機能に関する提案をいただいたり、私たち作り手の想いをお客様にしっかり伝えなくてはと感じた、というフィードバックをいただきました。
ソフトウェアエンジニア採用支援
また、ビジネス職への支援として、エンジニア採用に関する勉強会を開催しました。これは、お客様にご提案するエンジニア募集ポジションの要件定義をより的確に行えるよう、エンジニアの業務や関連用語への理解を深めてもらうことを目的としています。
具体的にはライブコーディングを交え、以下のトピックを解説しています。
- 開発中の新機能の紹介を通した実務の説明
- 要求分析から要件定義への詳細なブレイクダウン
- 要件定義に基づいたFigmaデザインのポイント
- デザインをもとにしたフロントエンド実装のライブコーディング
- バックエンドとの連携に関する説明
求人票相談会
ビジネス職向けに求人相談会を開催しました。エンジニア求人において候補者様の応募意欲を高める記載や表現は何か、 現役エンジニアの視点でお客様の求人票を実際に確認しながら改善提案を行いました。 「さっそく商談で提案してみます」という声もあり、非常に好評でした。
出張がもたらした3つの変化
ユビキタス言語の理解が深まった
今回の出張を通じて、ユビキタス言語(開発現場で共通理解を保つための語彙)への理解が一段と深まりました。開発現場ではコード上の用語だけを知っていても、実際の商談やサポートの現場でどんな文脈・目的で使われているのかをイメージしづらい場面が多々あります。ビジネス職のみなさんと直接対話したことで、言葉のニュアンスや使われるシチュエーションを立体的に把握できました。その結果、ドメインモデリング時に「モデルが適切な文脈を捉えているか」「命名が自然か」をより確信を持って判断できるようになり、実装品質にも良い影響が出ています。
ビジネス組織からのフィードバックと交流促進
これまでも組織間の距離は近かったのですが、出張を機により現場の声を直接的に聞けるようになりました。たとえばお客様にはあまり活用されていないと考えていた機能が、想定以上に利用されていることが分かるなど、機能の活用実態や課題を肌で感じ取れたのは大きな収穫でした。
さらに求人票相談会がきっかけとなり、CSのメンバーから「エンジニア求人のことで相談したい」と直接声が上がるようになりました。この反響を受け首都圏オフィスでも同様の相談会を開催したところ70名以上のビジネス職社員が参加し、ビジネス組織とプロダクト組織間の関係性を一層深めることができました。
マインドセットの変化
出発前はどこか「業務の一環のミーティング」という感覚でしたが、地方拠点の皆さんと接する中で意識は一変しました。熱量が非常に高く、私たちプロダクト職の話を、お客様との商談や採用支援に少しでも役立てようと、真剣に耳を傾けてくださいました。印象的だったのは、地元の美味しいお店という何気ない情報ですら、「お客様との会話のきっかけになる」と感謝されたことです。そのプロ意識の高さと、会話を重ねていく中で感じる「お客様の採用力向上に貢献するんだ」という強い意志に圧倒されました。
そんな皆さんと接し、持てる知識を惜しみなく共有しました。同時に、自身の周囲への関わり方や、プロダクトへの向き合い方は本当にこれで良いのだろうか?と、深く考えさせられる貴重な機会となりました。例えば、社内のランチ交流会(業務を越えた社内のつながりを作ることを目的に月に1度ランダムに設定された任意の複数人でのランチ会)で初めて接点を持ったビジネス職社員に、「何か私にできることはありませんか?」と積極的に声をかけるようになりました。これをきっかけに、お互いの意見交換をする場が生まれ、今後のプロダクト開発に活かせそうな期待を感じています。
まとめ
ビズリーチのプロダクト組織は「役割が交わる共創」を大切にしています。今回の経験を通して、私たちが「このUI/UXは本当にユーザーにとって最適なのか?」「この情報をビジネス職の仲間に共有すれば、お客様にプロダクトの魅力を伝えるきっかけになるのではないか。」といったことを自然に考え自分の専門領域を超えて行動することこそ、組織が目指す一つの姿なのだと思いました。
「役割を越える」ということは、最初は億劫で負荷を伴うかもしれません。まずは、ランチ交流会やビジネス職社員との交流会に参加してみる、ビジネス職の同期や知り合いに「最近どう?」と連絡してみるなど、身近な一歩から始めると、新たな発見や変化が生まれるのではないでしょうか。