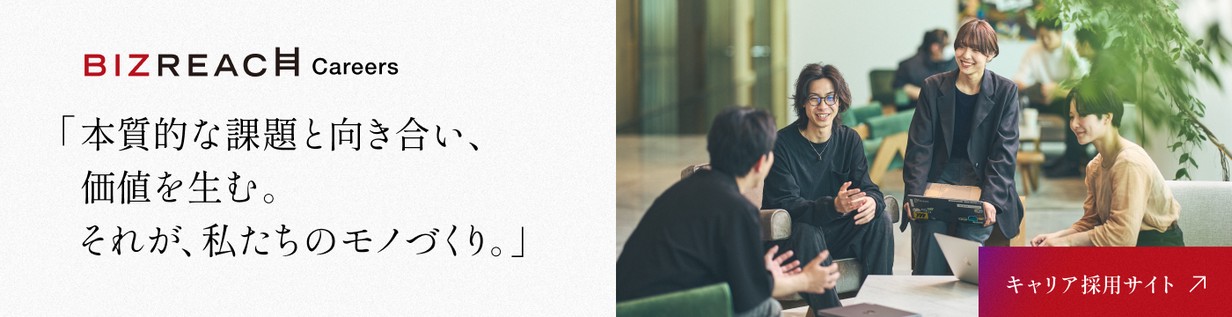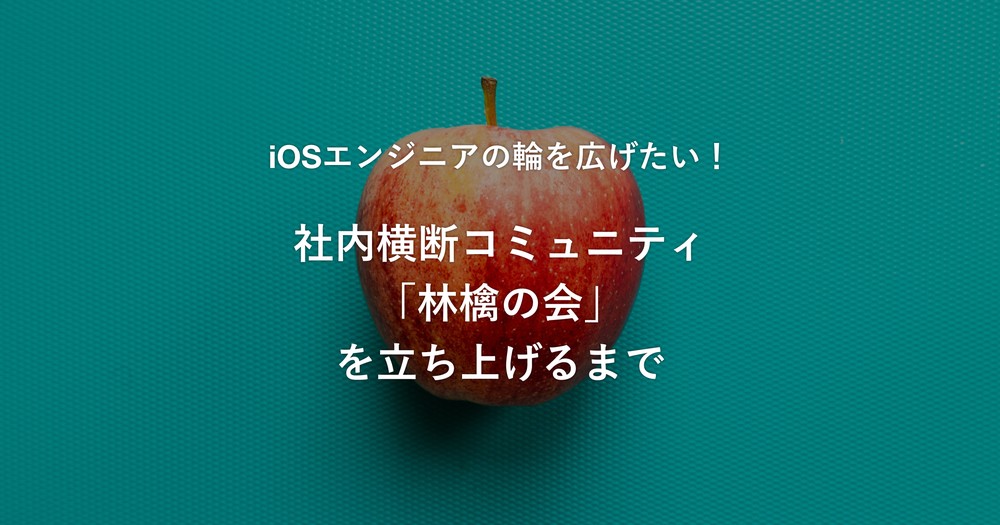1. はじめに:プロフェッショナルな働きに拍手を 〜成長を後押しするビズリーチの表彰文化〜
「握手・挙手・拍手」
株式会社ビズリーチでは、この3つの文化を大切にしています。なかでも「拍手」が自然と生まれる ビズリーチの象徴的なイベントが、「BizReach Awards」です。
「最高の仲間を、讃えよう。」「仲間の仕事に、熱くなれ」
そんな合言葉のもと、半年に一度、全国の社員が東京に集まります。そして、年次や職能に関係なく、プロフェッショナルな働きで成果を出した仲間を称え合います。
さらに、このアワードは単なる「称賛の場」ではありません。 今年の「BizReach Awards」では、プロダクト職の受賞者に、アメリカ・ラスベガスで開催される「Google Cloud Next」への参加という特別な機会が贈られました。この取り組みは、CTO外山の「世界の最先端を体感してほしい」という想いから実現しました。
なぜこの機会が生まれたのか、受賞者はどんな世界を体感してきたのか――。本記事では、その経験を社内に伝えるために開かれた、プロダクト交流会でのCTOと受賞者の対談を通じて、その背景や現地でのリアルな体験をお伝えします。
2. 受賞者が語る、現地の刺激と自身の変化
Google Cloudが主催する世界最大級のグローバルカンファレンス、「Google Cloud Next」。世界中から数万人規模のプロダクト人材が集まり、最新のプロダクトやテクノロジーに関する発表・セッションが多数開催されます。
今回、受賞者たちは現地でどんな刺激を受け、どのような変化を感じたのでしょうか。
圧倒的なスピード感で進むAI活用
受賞者たちは、生成AIの最新技術やグローバル企業の導入事例から、多くの学びやヒントを得ていました。 というのも、現地では会場内外にAIを活用した様々な仕掛けが溢れていたからです。 Expoと呼ばれる展示会では、世界中の企業がブースを構え、未発表の新機能やプロダクトを体験することができました。また、セッションでは技術の進化がビジネスや働き方をどう変えていくのか、その具体的な未来像が語られました。自分たちの普段の仕事にもつながる発見があったようです。
例えば “Automate Data Pipelines with AI Agents in BigQuery” というセッションでは、人間が自然言語で指示するだけで、データパイプラインを自動で構築してくれるという「Data Engineering Agent」が紹介されました。あるエンジニアの受賞者は、「これは、エンジニアがより本質的な課題解決に集中できるようになる画期的な技術だ」と、強い衝撃を受けたと言います。
また、デザイナー視点ではクリエイティブコンテンツの制作プロセスが根本的に変わる可能性を感じた受賞者もいました。"Accelerate Creative Media Content with Gen AI" のセッションでは、Imagen 3(画像生成)、Veo 2(動画生成)、Lyria(音楽生成)といった複数のAIを組み合わせることで、ブランド定義さえすればコンセプト立案からメディア制作までを高速で実行するワークフローが紹介されました。仕事の仕方を根底から変えるような体験に出会ったことで、あらゆることに好奇心を持ち、自らもより積極的にAIに触れながら、新しい活用方法を模索していくようになったと言います。
革新的なチャレンジの根底にある、現地エンジニアのマインドセット
セッションやExpoから技術的なインスピレーション多く得たのはもちろん、それと同じくらい受賞者の心に残ったのは、現地の空気そのものでした。 中でも、ある受賞者が特に影響を受けたと語ったのが、現地で出会ったエンジニアたちから感じた、仕事に対する圧倒的な「貪欲さ」です。
Meetupや懇親会の場に集まったエンジニアたちは、1分1秒を惜しむように熱い議論を交わしていました。互いに次々に質問をぶつけあい、今後作りたい物について夢や目標を語り合う。世界中から優秀なエンジニアが集まり直接交流できる貴重な機会だからこそ、その時間を最大限に活かし、一つでも多くのものを得ようとする姿勢を感じ取ったと言います。
なぜ、彼らはこれほどまでに貪欲なのか。その受賞者は、背景に日本との雇用文化の違いがあるのではないかと考えます。
アメリカの企業は、成果を出せなければ簡単にキャリアを失いかねない世界です。 だからこそ、彼らは常に学び、新しいチャレンジをして成果を出すことに必死なのです。そして、Googleの「20%ルール」(会社の仕事に一応関連しているが自分の主要な職務の範囲外にあるアイデアのために、就業時間の20% を自由に使える制度)に見られるように、企業側にも挑戦を全力で後押しする文化が根付いているのではないかと思います。リスクがあっても、より多くのリターンがあれば迷わず挑戦する。「まずはやってみよう」「失敗したときに考える」というスピーディーかつダイナミックに変化を生み出す現場の前向きな雰囲気を肌で感じたようです。
この体験によって、帰国後の自身の行動も大きく変わったと言います。 普段は業務で関わる限られた仲間で話すことが多く、固定化されつつあった視点を広げるため、社外の勉強会へ積極的に足を運ぶようになりました。ラスベガスでの経験から「同じプロダクトでも、人によって全く違う視点で見ている」という事実を改めて実感したからです。
技術そのものだけでなく、「なぜこのプロダクトが生まれたのか?」「どんな人が、どんな想いでこれを創ったのか?」という思想や哲学を直接感じる機会に、価値を感じているそうです。
このように、受賞をきっかけに得た海外でのリアルな体験が、自身の行動をも変え、さらなる成長につながっています。
3. なぜこの機会を作ったのか?CTOの想い
Google Cloud NextのセッションはWebでも公開されており、現地に行かなくても情報を得ることはできます。それでも、なぜCTOは「わざわざ現地まで足を運ぶ」機会を用意したのでしょうか。
CTOの外山は、こう説明します。
「現地の街並みや人々の表情、振る舞いなど、実際に足を運んで体験しなければ感じ取れない“アメリカならではの意思決定の思想”を、リアルに身体で体感してほしい。」
アメリカのDXやAI技術の活用は、日本よりも遥かに進んでいます。しかし、その差は単なる技術力だけでなく、意思決定の背景や文化の違いに根ざしています。だからこそ、カンファレンスだけでなく、エンタメや日常生活も含めて現地の空気を直接体験することに大きな価値があると考えています。
特にAIの活用やプロダクト開発のスピード感など、アメリカの現場は日本とは大きく異なります。なぜ今その技術が盛り上がっているのか、これからどのようなトレンドが来るのか――それは現場の空気感や、世界中のプロダクト人材との雑談の中にこそヒントがあります。
実際、受賞者たちからは「セッションの内容以上に、現地での生活や観光を通じて得た気づきが多かった」という声もありました。出発前にCTOから直接伝えられた想いを胸に、それぞれの観点から多くの刺激を受け取ってきたようです。
ただし、アメリカの現状をそのまま日本に取り入れれば良いわけではありません。アメリカのモデルは、その国の文化や課題感に合わせて進化してきたものです。私たちは、アメリカを参考にしつつも、自分たち自身が直面している課題や状況と向き合い、なぜそうするのか、どうやるべきなのかを考え抜くことが重要だと考えています。
「大きな成果を残したBizReach Awards受賞者だからこそ、ビズリーチの現状やプロダクトの課題をしっかりと理解し、この先の自身のプロダクト開発に活かしてほしい」――これが、CTOの想いです。
4. おわりに:次にこの場に立つのは、あなたかもしれない
今回のプロダクト交流会には、Visionalグループ全体のプロダクト職社員が約50名参加しました。受賞者は自らの経験や学びを多くの参加者にシェアし、参加者たちも改めて表彰された仲間を讃える拍手を送りました。
私自身、BizReach Awardsの表彰式や交流会で直接受賞者の話を聞く中で、「次は自分もこの場に立ちたい」と強く感じました。特に、受賞者と共に働くチームメンバーや、採用・育成に関わっていた先輩社員が受賞を自分のことのように喜び、温かく迎える様子が心に残っています。仲間同士で讃え合い、高め合う――これこそが私が好きな ビズリーチの文化の一つであり、それが会社全体に根付いていることを改めて実感しました。
この経験を通じて、「日々の仕事でももっと挑戦し、価値を生み出したい」という前向きな気持ちが強まりました。それは他の参加者も同じだったようです。
さて、次に拍手を浴びるのは、この記事を読んでいるあなたかもしれません。新しい価値を生み出したい、もっと成長したい――そんな想いを持っているなら、ぜひ一緒に新しい未来を創りませんか?
もし少しでも興味を持っていただけたら、採用ページをご覧ください。Visionalグループでは、プロダクト職の採用活動を積極的に行っています。