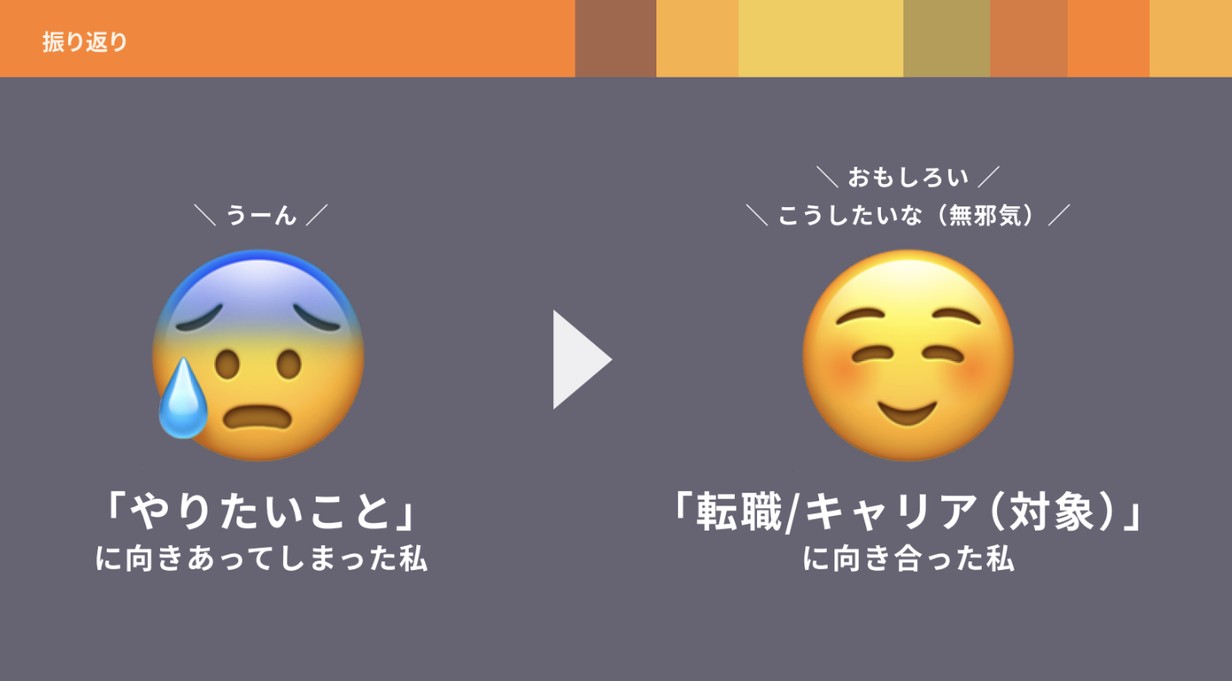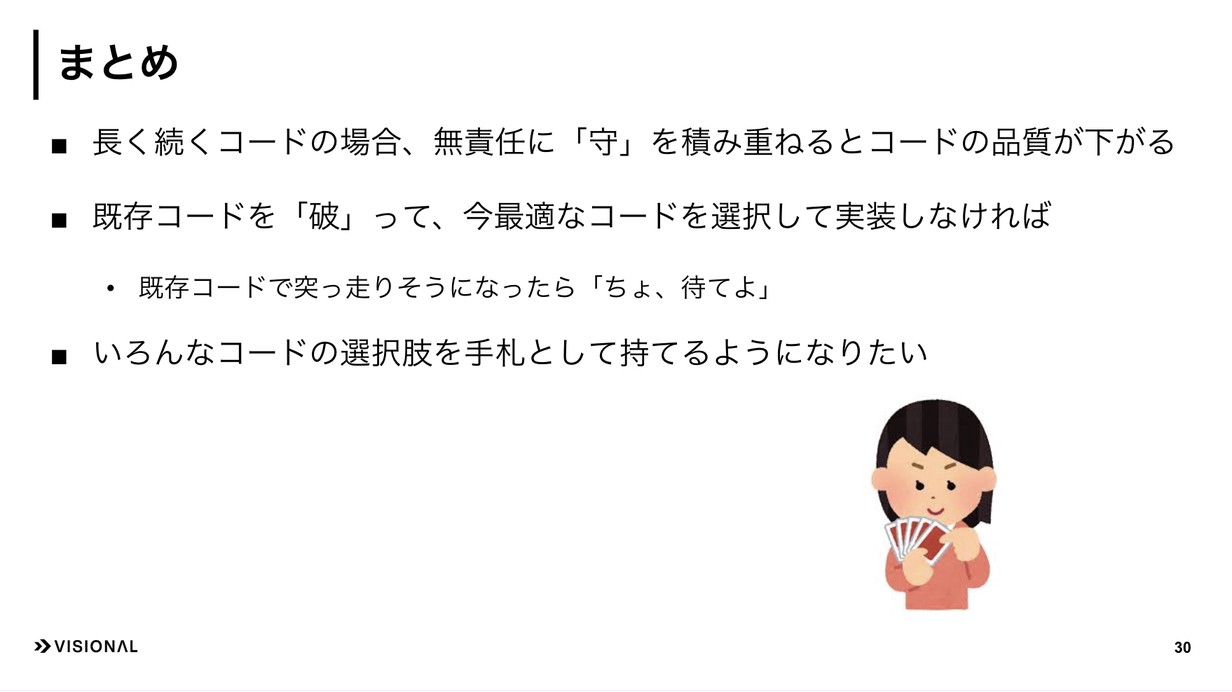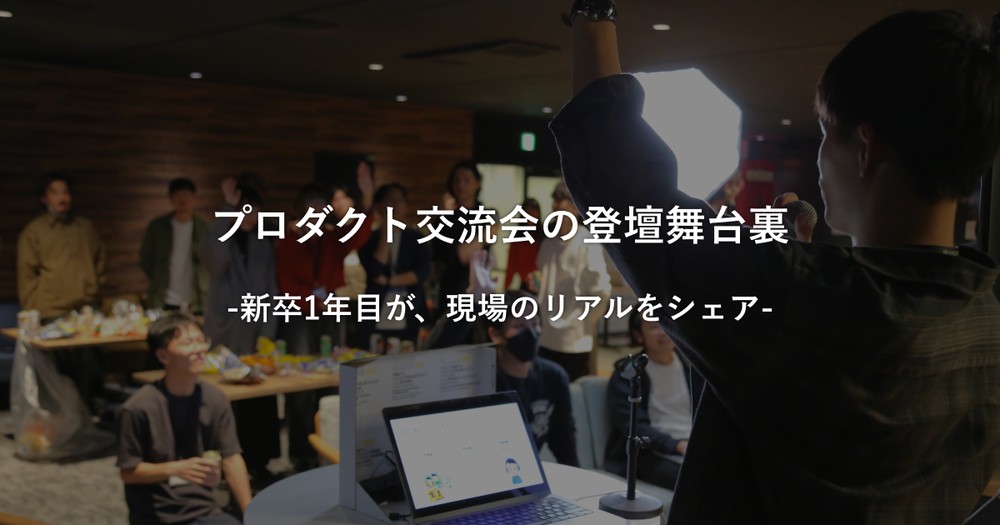「プロダクト交流会」は、Visionalグループ各社に所属するプロダクトに関わるメンバーの交流を目的としたLT大会です。コロナ禍によって薄れてしまった横のつながりを復活させるべく、2023年より有志メンバーによるプロジェクトとしてスタートしました。
昨年10月に開催された会のテーマは「秋の新卒フィーチャー会」。 2024年4月に入社したプロダクト職(エンジニア/デザイナー)の新卒社員が、現場に配属されてから約半年間のリアルな苦悩や学びをシェアしてくれました。またその登壇を受けマネージャーやメンターと登壇の振り返りを行ったので、その様子をインタビュー形式でお伝えします。
なお、筆者は2023年に新卒入社したエンジニアの澁谷です。筆者も過去に新卒社員として同じテーマで登壇しています。(過去の記事はこちら)。
Case1: 新卒デザイナーの好奇心から始まる挑戦
まずはこちらのお2人にお話を伺いました。
プロフィール
計良 奈純(通称:けらちゃん)
新卒1年目プロダクトデザイナー
「ビズリーチ」の求職者様側プロダクトのUI/UXデザインを担当
趣味:ボードゲーム・ミュージカル鑑賞
福田 佳世子(通称:かよちさん)
新卒7年目プロダクトデザイナー/デザインマネージャー
趣味:犬、食器収集
自分は「何がしたいのか」考え続けた2ヶ月
—澁谷:プロダクト交流会、登壇ありがとうございました。記事を読んでいるみなさんに向けて、発表の内容をあらためて教えてください。
—計良(けら):今回は、1on1でかよちさんに聞かれていた「けらちゃんは仕事を通じて何がしたいの?」という問いに対し、携わった仕事を通してこの数ヶ月で言語化したことについて発表しました。
問いをいただいた直後は「何をやりたいか」についてぐるぐる考えていて答えが浮かばなかったのですが、今直面している仕事に対して好奇心をもって深く向き合った時に「今行っている仕事の価値に向き合いたい」という気持ちが自然と湧き上がってきたことに気づけました。
ー澁谷:素敵な学びですね!ビズリーチには「好奇心からすべてがはじまる」という社員の心得もあります。まさに「好奇心」を持つことが突破のきっかけとなったのですね。かよちさんはそもそもなぜ「何がしたいか」という問いを投げかけられたのですか?
—福田(かよち):「何がやりたい?」って聞き方はコーチングとしてはあまり良くなかったなという反省がありますが(笑)。質問の意図としては、配属からの2ヶ月間で自身の目標を設定しておく必要がありました。そのために「何がやりたい?」と聞いていたのですが、それは仕事を知らないと分かってこないよね、色んな仕事をして見つけていけるといいよねと、と話していました。
「今行っている仕事の価値に向き合う」ことが自分の「やりたいこと」
—澁谷:いきなり自分が何がしたいかはなかなか見つかりませんよね。僕も当初は同じ状況だったと記憶しています。やりたいことに気づくまでに、この仕事はやってて面白いなとか、逆にこれは苦手かもなといった紆余曲折はありましたか?
—計良(けら):それがなくて(笑)。なんでもやりたい!という気持ちでした。最初はSQLを使ったデータ分析や社内資料作成、自社ブログのキービジュアル作成など、幅広い分野の業務に関わらせていただきました。
今思うと、チームメンバーはグラフィックが強いとか分析が強いとか、強みがはっきりしている人が多いので、自分も何か強みと言えるものを獲得しなきゃという焦りもあったと思います。
Visionalには「価値あることを、正しくやろう」というバリューもありますが、業務で行っていることは正しいこと・価値があることだと思っているので、結果的になんでも楽しめたんだと思います。
—澁谷:業務自体が好きかどうかではなく、その業務はどんな価値を提供しているのかが分かると腑に落ち、はっきり「やりたいこと」と感じたのですね。かよちさんは当時けらちゃんの状況をどのように捉えていて、どんなサポートをしていましたか?
—福田(かよち):このときは、今の業務の中からけらちゃんがどういう業務に価値を感じて、かつそれが組織貢献に紐づけられるのか、自身の可能性を広げられるタスクをアサインするように意識していました。だから全く一貫性のないタスクをアサインしていました(笑)。
そしてさまざまな業務に触れていく中で、けらちゃんから、抽象度の高いものを具現化していく強みを発揮することでプロジェクトを前に進めていくことがデザイナーの価値なんじゃないかという仮説が出てきて、だからもっとUIを作れるようになりたいという話をしてくれました。
さまざまな業務を通じてどういうものに自然と心が動くのかを感じながら、今自分が何をやりたいのか具体まで落とし込んでいけたのはよかったなと思います。
—澁谷:可能性を広げるために、幅広い業務の経験を積んでもらうことで、自分の価値観を見つけていくことができたんですね。
みんなが直属の後輩のように育てる文化
—澁谷:当日の発表には約80人の社員が集まりました。率直にどうでした?
—計良(けら):本当にいい先輩たちに囲まれて最高の組織にいるなあと。あったかいなあと感じました。 同じチームの先輩だけでなく、所属組織内のプロダクトマネージャーだったり、聴いてくださっているみなさんが直属の後輩かのように応援の声をかけてくれていたので安心して発表することができましたし、感動しました。
—澁谷:対面での発表や交流の場は、組織の温かさを肌で感じることができるいい機会ですよね。かよちさんは発表を聴いて、いかがでしたか?
—福田(かよち):とても感動しました。配属後の私からの問いにちゃんと向き合い自分で見つけにいくことをしてくれましたし、改めて私も配属当初からこれまでのことを思い出し心があったまりましたね。すごく嬉しくなりました。「みんなで育てる」という意識が強い私のチームはけらちゃんの成長を見てお祭り騒ぎでした(笑)
解像度をあげてより高い価値を出せるデザイナーを目指して
—澁谷:発表中かよちさんのチームが盛り上げてくれたおかげで、会場のみなさんにも楽しんでいただけたと思います。最後にけらちゃんが考える「価値」についてあらためてお聞かせください。
—計良(けら):前提、自分が提供できる価値が何かはまだ分かっておらず、交流会後もずっと考えています。ただ、今は目の前の業務に好奇心を持って向き合っていくことで価値への解像度をあげて、より良い価値を提供できるようになりたいです。特に先ほどの話でも出てきたUIをしっかり作れるようになって、デザイナーとして具現化していく力をつけていくことに今は愚直に向き合っていきたいです。
—澁谷:お2人ともありがとうございました!
Case2: 新卒エンジニアの「守」から「破」への変化
続いてはこちらのお2人にお話を伺いました。
井上 真悠子
新卒1年目プロダクトエンジニア
「ビズリーチ」の企業様側プロダクトの開発を担当
趣味:バスケットボール観戦・ドラマ鑑賞
永德 泰明
新卒8年目プロダクトエンジニア
「ビズリーチ」の企業様側のプロダクトの開発を担当
趣味:登山、料理
「守」で生きてきた学生時代
—澁谷:プロダクト交流会、登壇ありがとうございました。 記事を読んでいるみなさんに向けて、発表の内容をあらためて教えてください。
—井上:修行における3つの段階を表す「守破離」という言葉がありますが、私は師の教えや型を忠実に守り、身につける段階の「守」でこれまで生きてきたと感じています。でもエンジニアの仕事をする上で「守」のままだとダメだと思っていて、それで外部から良いものを取り入れ、発展させる段階の「破」にいくためにはどうしたらいいかを考えて行ったことを発表しました。
—澁谷:ありがとうございます。「守」で生きてきたということですが、どのような時に自分は「守」だと感じましたか?
—井上:基本空気を読むタイプですし、これまでの受験や勉強も教えてもらったことをそのままやってみることで上手くいった人生だったと思います。
社会人になって「守」だけじゃダメだなと思ったのは、コード修正タスクを行った際のことです。既存のコードと似た部分を模倣して実装していたのですが、レビューを出した時に先輩からの「なんでこういう風に書いたんですか?」という質問に答えられなくて。その時にエンジニアとしてあるべき姿じゃないなと思いましたし、今の状況で最適なコードを書いていかないと将来自分を含めたエンジニアが困ることにもなります。 そういった「守」の行動をしていた自分に気が付き「破」にいきたいと思いました。
—澁谷:井上さんのメンターである永徳さんは、この状況をどのようにみられていましたか?
—永徳:そうですね、私たちが携わっている「ビズリーチ」はリリースから10年以上が経っており、現在では最適化されていないコードが含まれています。そのため実装時に迷うことが多いのは事実です。井上さんは直面した問題の言語化に困って、それで似たコードを模倣して実装していると捉えていました。
—井上:なんとなくそれがダメなのは自覚していたのですが、なぜダメなのかをうまく言語化できず、向き合うことができていなかったですね。
自身の成長に向き合ってくれる先輩方
—永徳:井上さんは問題に直面したときに1日中悩んでしまうことがあったので、キメ細かくヒアリングしてフィードバックサイクルを早くしようと提案しました。毎朝チーム内で共有事項を話す朝会があるのですが、その後に10分程度コードを一緒に見て相談する時間を設けました。 その場で一緒に言語化しながら進めることで、徐々に一人で進められるようになっていきましたね。
—井上:本当にありがたい対応でした。自分は考え込んじゃうタイプなので毎日フィードバックをいただける機会を作ってもらえたことで、以前よりも速くPDCAサイクルを回しながら永徳さんの考え方を吸収していくことができ、「破」の感覚が掴めてきたと感じています。
—澁谷:井上さんの個性に合わせたサポートをしていたんですね。新卒社員の身としてはとてもありがたいと思います。井上さんはこのチームに配属されてからの半年間、どのような環境だったと感じていますか?
—井上:自分の成長にすごく向き合ってくださる方が多いです。成果物に対してすぐにフィードバックしてくださったり、他の方がやればすぐ終わるタスクでも自分の成長のためにタスクを割り当ててくれるのはありがたいなと感じています。
—永徳:裏話として、井上さんは目標設定のときに「技術的難度が高く、複雑性・新規性のある開発をできるようになりたい」と希望していましたが、当時の上長は案件のリスク等を加味しながらアサインを慎重に検討していました。
もちろんさまざまなことを考慮する必要はありますが、あるチャレンジングな案件があった際に、井上さんにとって成長の機会になるはずだと思い、僕から、自分を含め周りもサポートするということを上長に話し、その案件を最終的に井上さんに任せてもらえることになりました。
—井上:そのような動きをしてくださっていたのは知らなかったです!ありがとうございます。
—澁谷:永徳さんは井上さんの日々の頑張りを見ながら、機会をつくってくれたり、さまざまな側面で積極的にサポートしてくださっていたんですね。
根拠のある意見を提案できるエンジニアを目指して
—澁谷:当日の発表はいかがでしたか?
—井上:発表中に「わかる〜!」と声を上げて共感してくれる人が多くて嬉しかったです。また、違うプロダクトに関わる方からはそういう悩みがあるんだね、という声もいただきました。 私は入社後は今携わっている「ビズリーチ」プロダクトしか知らないのですが、歴史が長いプロダクトに関わっているからこそ、いいコードとあまり良くないコードをどちらも見れる環境は貴重なんだということも認識できました。
—澁谷:最後に、井上さんがエンジニアとして目指す姿についてお聞かせください。
—井上:今は引き続き、先輩たちから実装の選択肢を学んで吸収していく時期と捉えています。まだ自信と根拠を持って選択できていないので、それができるように頑張りたいなと思っています。そして、後輩が入社した際には自信と根拠を持って意見を伝え、サポートできるようにがんばります。
—永徳:是非もっと大きな課題に向き合えるような力をつけていってほしいですね。
最後に
2組のインタビュー、いかがだったでしょうか。
先輩たちは新卒社員の成長を支えるために、個々が直面する課題に寄り添ったサポートをし、新卒社員は自分の成長に向き合い、自分のやりたいことを見つけるために、様々な業務に挑戦している様子が伝わってきました。
私も1年前、できないことだらけの状況に置かれていましたが、周りの先輩のサポートを受けながら自分の成長に向き合っていくことで、少しずつ自信を持つことができました。お互いに成長を信じ合える環境が絆を深め、組織全体の成長につながるのだと実感しています。
プロダクト交流会の新卒フィーチャー会はこれからも継続して開催していく予定です。新卒と直接関わりのない社員も新卒を仲間として温かく歓迎できる場として、今後も続けていきます!